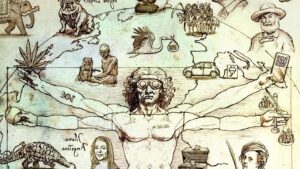今回は「第8章:嘘と真実」の続きです。
第8章を読んでいない方は理解が難しいと思うので先に第8章をお読みください。

前章では情報格差についてお伝えしました。
今回は雇用の未来について説明していきます。
ご存知のようにほとんどの日本人は終身雇用がいつまでも続くものだと思っている状態です。
しかし残念ながら終身雇用は既に崩壊しています。
雇用に対する理解を深めるため歴史から振り返っていきましょう。
第9章:雇用の未来
雇用契約の土台となっているのは労働三法です。
これらの法律がいつ誕生したのかご存知ですか?
- 労働組合法が施行(1946年)
- 労働関係調整法が施行(1946年)
- 労働基準法が施行(1947年)
どれもまだ70年くらいしか経っていません。
たいして歴史のない法律なのですが現代人の中では既に常識となっています。
そして終身雇用を語る上で欠かせないものは労働者派遣法です。
もしかすると「どうして派遣法?」と思われたかも知れません。
実は正社員の割合は年々減ってきており現在では全労働者の60%しかいないのです。
そしてここを理解するための鍵となってくるのが労働者派遣法ということになります。
労働者派遣法は1986年に施行されました。
まだ30年しか経っていない法律なんですね。
この法律は一体何をしてきたのでしょうか?
わかりやすく順番に見ていきましょう。
当初は専門性の高い特定の13業務だけを派遣可能にするという法律でした。
これは今とはまったく別の法律です。
1996年、1回目の改正で派遣可能な範囲を13業務から26業務へ拡大しました。
ここではまだほんの一部の業務だけが派遣を許可された状態です。
しかし1999年、2回目の改正で法律の内容を大きくひっくり返します。
特定の業務だけ許可という形から特定の業務以外は許可という形に変更しました。
医療や士業、製造業を除いたすべての業務で派遣を許可したのです。
これにより派遣社員が一気に身近な存在になります。
2000年、3回目の改正では紹介予定派遣が導入されました。
これは直接雇用の可能性を前提に派遣社員として働く制度です。
正社員と派遣社員の間と言えるでしょう。
2004年、4回目の改正では製造業の派遣が許可されました。
2006年、5回目の改正では医療と士業も一部解禁となります。
2007年、6回目の改正では派遣可能期間を伸ばしました。
この時点でほぼすべての業務において派遣が可能となっていることにお気づきでしょうか?
なんと施工開始からたったの20年でまったく別の法律になってしまったんですね。
そして2008年にはリーマンショックが起こります。
これにより派遣切りやワーキングプアなどの問題が浮上しました。
2012年、7回目の改正では日雇い派遣の原則禁止などいくつか制限が設けられることになります。
2015年、8回目の改正では労働者派遣事業がすべて許可制になりました。
これは悪質な業者は潰して労働者を保護しましょうというのが表向きの名目です。
言い換えれば小さな派遣会社を排除したということになりますね。
2020年、9回目の改正では同一賃金同一労働が大企業で導入されました。
この改正はとても話題になったのでご存知の方も多いのではないでしょうか?
2021年、10回目の改正は教育関連の微調整です。
2021年、11回目の改正では同一賃金同一労働が中小企業でも導入されました。
そして看護師の派遣まで一部解禁となります。
どうでしょうか?
これが現在に至るまでの派遣者労働法の流れです。
最初はわずかな専門職だけ派遣可能でした。
でもあと少しですべての派遣が可能になります。
待遇の差も縮めました。
これから何が起こるかわかりますか?
正社員と派遣社員の境目がなくなります。
これまでの歴史を見てきた方ならもうお気づきなのではないでしょうか?
労働者派遣法が時代に合わせて変化してきたわけではありません。
そもそも初めから雇用の形を変えるために導入された法律なのです。
そしてこれに合わせて動いているものがあります。
それは一体何かというと銀行法改正です。
2021年7月、ゴールドマンサックスが日本で銀行業の免許を取得しました。
2021年11月には銀行法が改正されます。
なんだか凄いタイミングですよね。
果たしてこれが何を意味するかわかりますか?
改正銀行法では銀行の企業に対する出資規制が5%から100%になりました。
出資規制が100%になれば銀行が企業の経営権を握ることができます。
つまりこれにより外資が日本企業をコントロールできるようになったということです。
日本は99.7%が中小企業で構成されています。
その中小企業が現在どのような状況かご存知でしょうか?
多くの企業はコロナ融資を受けて経営をギリギリつないでいる状態なのです。
無利子無担保のゼロゼロ融資で無理やり延命させられています。
2022年には融資の返済期限が訪れていよいよ返済がスタートしました。
中小企業にはもうこれ以上振り絞るほどの余力なんてありません。
これまでお伝えしたようなあらゆる緊急事態も追い打ちをかけてきますからね。
これから中小企業はバタバタと倒産します。
歴史的な大失業時代の到来です。
誰もが知る有名企業ですら廃業が始まりました。
サクマ式ドロップス製造会社が廃業へ 「火垂るの墓」にも登場 コロナ禍と原材料高で経営悪化
廃業ではなく外資に買われる企業もあるでしょう。
しかしそのとき雇用契約は守られると思いますか?
Twitterのエリート社員ですら買収直後に社員の半数である4,000名が突然解雇される時代ですよ。
これは事前告知なんてなく法律さえ無視で解雇が行われました。
日本は全企業の99.7%が中小企業です。
日本で99.7%を占める中小企業の「正社員」が崩壊するのはもう時間の問題なんですよ。
果たして大企業の「正社員」は無関係でいられるでしょうか?
「あたりまえ」は言い換えると「多数派」という言葉になります。
人数にしても大企業の正社員は30%もいません。
そのたった30%の人たちが「あたりまえ」になると思いますか?
さすがになりませんよね。
残念ながら「正社員」とか「派遣社員」なんてものは過去の遺物となります。
2019年、経団連の中西会長は終身雇用が守れないことを公の場で断言されました。
ある意味これが事前告知とも言えるでしょう。
正直言って、経済界は終身雇用なんてもう守れないと思っているんです。どうやってそういう社会のシステムを作り変えていくか、そういうことだというふうに(大学側と)お互いに理解が進んでいるので」
https://news.ntv.co.jp/category/economy/429964
ここでは社会のシステムを作り変えていくと仰っていますね。
日本の年金システムや雇用システムが崩壊していることなんて算数ができる人なら誰だってわかることです。
労働者派遣法や銀行法改正には竹中平蔵が深く関わってきました。
その竹中平蔵がずっと何を提唱してきたかご存知でしょうか?
ベーシックインカムなんですね。
この雇用システムの破壊によって政府からお金を支給してもらうベーシックインカムへと繋がります。
東京都では生活困窮者に対してお米の支給が始まりました。
1世帯に米25キロ支給検討 物価高騰で生活困窮者支援へ 東京都
アメリカやイギリスでも同様に生活困窮者に対して支給が始まっています。
そしてこの流れからベーシックインカムへと繋がっていくのです。
自分や家族の身を守るための通貨を手に入れられなかった人には昆虫食が支給されるようになっていくでしょう。
これが雇用についての歴史と未来です。
あらかじめ枠組みができているので流れが大きく変わることなんてありません。
もし歴史を知らないと何かが起こるたびにこれまでの常識が突然崩壊してしまったかのように感じます。
しかし歴史を見れば予定通りに物事が進んでいるだけということがよくわかるのではないでしょうか。
常識というものについて少し触れておきます。
日本で外食産業が栄えたのは1970年以降です。
- すかいらーく1号店(1970年)
- ロイヤルホスト1号店(1971年)
- マクドナルド1号店(1971年)
- セブンイレブン1号店(1974年)
これらはどれもたった50年の歴史しかないのですが現代人にとっては当たり前の存在ですよね。
でも昭和のおじいちゃんおばあちゃんからしたら当たり前ではありません。
少し前まではLINEやTwitterでメッセージをやりとりするなんてことも当たり前ではありませんでした。
それが今ではメッセージのやりとりどころか買い物までSNSでおこなっています。
しかしこれらも当たり前になってからまだ10年も経っていないんですよ。
いつのまにか「非常識」は「常識」になりました。
少し前までガラケーでEメールのセンター問い合わせをしていませんでしたか?
携帯をパカパカ開いたり折ったりしていたことすら忘れてしまったのでしょうか?
「常識」もまたいつのまにか「非常識」になりました。
このように常識と非常識なんて気がつかない間に切り替わっているものです。
そして多くの場合それは政府や企業の思惑に動かされます。
あなたは世の中の変化の速さを意識したことがありますか?
ほとんどの人は変化の速度が一定だと思っています。
しかし実際のところ変化の速さというのは指数関数の曲線を描くのです。
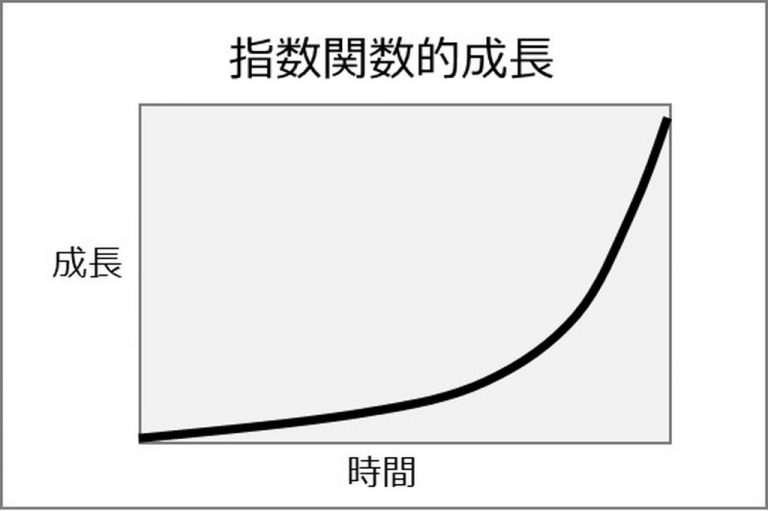
1990年、人々はまさか自分がパソコンを使う日がくるなんて想像もしていませんでした。
しかし時間が経つにつれて誰もが使うようになりました。
2000年、人々はまさか自分がスマートフォンを使う日がくるなんて想像もしていませんでした。
しかしスマートフォンはパソコンよりも早くみんなが使うようになりました。
今では小学生ですら当たり前のように持っています。
そして2022年、人々はまさか自分が仮想通貨を使う日がくるなんて想像もしていません。
しかしあと数年もしたら誰もが当たり前のように仮想通貨を使うようになっています。
そしてこれは本当に一瞬で切り替わるでしょう。
最後に世界的起業家であり投資家でもあるピーター・ティールの言葉を貼っておきますね。
ピーター・ティールはドナルド・トランプの大統領就任に貢献した陰の大統領と言われる男です。
常識は崩壊したときに初めて、それが間違いだったと気づく
以上、「第9章:雇用の未来」でした。
次で最終章となります。
これまでの話をすべてまとめていくのでぜひ最後までお読みください。
「第10章:生き残る人」へと続きます。